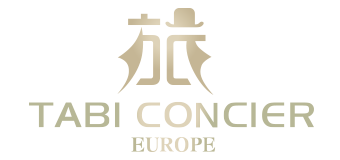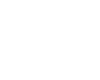旅コンシェルを利用してオリジナルな旅行プランを実現された方の
旅のご感想を紹介します。
旅コンシェルを利用して
オリジナルな旅行プランを
実現された方の
旅のご感想を紹介します。
定年退職を機にかねてより行きたかったチェコへいくことに。
2025年9月、鉄道と教会建築の写真を撮る為にお出かけになった横浜市の安藤様。
個人旅行でしか行くことが出来ない都市を目的地に観光されました。
-
スケジュール 宿泊地 1 日本発→ウィーン
ウィーン泊
2 ●列車でブルノ経由プラハへご移動
プラハ泊
3 ◎プラハ市内観光
プラハ泊
4 ●列車でターボルへご移動
◎ターボル市内観光ターボル泊
5 ◎チェスキー・クルムロフ観光
ターボル泊
6 ●列車でリンツへご移動
◎リンツ市内観光リンツ泊
7 ●列車でウィーンへご移動
ウィーン泊
8 ウィーン発
帰国の途へ機内泊
9 →日本着
-
お客様のご利用ホテル
-
ウィーン
-
プラハ
-
ターボル
-
リンツ
-
-
旅のきっかけ
子どもも成人となり、私自身も40年近く勤めた会社を定年退職した2025年、夏休みを利用して、かねてより行きたかったチェコへ行くことを思い立ちました。
私の旅の目的は、「現地の風景をバックに鉄道の写真を撮ること」と「チェコの各都市に残る教会建築を見学すること」です。
こんな旅行ですから、やはり個人旅行。ヨーロッパ個人旅行について経験豊富な旅コンシェル様にいろいろご相談・手配いただいた結果、チェコ旅行が実現しました。
-
聖ヴィート大聖堂とトラム
-
ブルノの街
午前10時ごろウィーンHbfをレイルジェットで出発して、ブルノの街へ向かいました。モラビアの中心都市のブルノで見たかったものは二つあります。一つは聖ペトロ聖パウロ大聖堂、もう一つはブルノ本駅で入換え用として活躍しているはずの210形電気機関車です。しかし、レイルジェットで進入した駅構内には全く210形電気機関車の姿が見えません。どうも直近2年くらいの間に短編成の新しい電車が導入されたようで、入換え用の機関車はお役御免になりつつあるようです。残念!
しばらく辺りを確認した後、まずは聖ペトロ聖パウロ大聖堂を見学することにしました。ブルノの街も第二次世界大戦で空襲を受けていますが、幸い大聖堂には大きな被害はなっかたようです。街にはそこかしこに赤い屋根の古風な建物が残っており、大聖堂とあわせて大変情緒のある風景になっています。
聖ペトロ聖パウロ大聖堂は、ブルノ本駅から歩いて20分ほど、街の中心部ペトロフの丘の上にありました。80mを超えるゴシックの尖塔が青空を衝いて聳え立っています。元々この大聖堂は12世紀に建てられた礼拝堂が起源とのことです。ゴシックの尖塔は20世紀初頭に追加されたものですが、大聖堂の外陣部分は、石積みが古めかしく、昔のままのようでした。後で知ったことですが、この大聖堂は、10コルナコインの裏側にもデザインされています。モラビアを象徴する建造物なのでしょう。 -
聖ペトロ聖パウロ大聖堂
-
ヴィートコフの丘
かつてのフス戦争で戦場となったヴィートコフの丘は、ブルタヴァ川の東岸側から街を俯瞰するのに大変良い場所です。
この丘を登る歩道からプラハ本駅を出入りする列車を撮影することができます。遠くにプラハ城やティーン教会、火薬塔、ストラホフ修道院等、主要な名所を望むことができるのも大変魅力的です。朝の光が大変きれいですから午前中に訪れるのが良いと思います。地元の方も結構散歩に来られて、この景色を楽しんでいるようでした。
-
ヴィートコフの丘
-
聖ヴィート大聖堂
プラハと言えば、プラハ城。プラハ城と言えば、やはり聖ヴィート大聖堂が大変目立ちます。ドイツでよく見るような典型的なゴシック建築です。外観の写真を撮っていて私の興味を惹いたのは、大聖堂の壁面から飛び出るように取り付けられているガーゴイルです。大聖堂を下から見上げた時に大変目につきます。ガーゴイルは機能的には雨樋です。ゴシックの大きな建物によくあるようです。このガーゴイル、とても装飾性にも優れていて、見ていて飽きません。日本の寺院建築の木鼻もなかなか面白いのですが、こちらは十分な機能性も有しています。さすがヨーロッパの人の考えることだなと改めて感心してしまいます。
プラハ城からの長い階段を下りて、マーネスフ橋を渡って、再び旧市街へ向かいます。丁度、トラムが橋を渡って来ました。
1960年から1980年代に製造されたタトラT3型です。古いものが大切に残されている街。プラハはそんな街です。
-
聖ヴィート大聖堂のガーゴイル
-
ターボルの街
そもそもターボル訪問の目的は、ターボルから出ている支線に乗ってベヒニェへ行き、ベヒニェ駅の手前に架かる鉄道道路併用橋のレインボーブリッジを渡る113形電気機関車牽引の列車を撮ることにありました。
ところが、ターボルの駅で案内を確認すると発車番線のところに「BUS」の表示が出ています。「えーっ」と思いましたが、事情はすぐに判かりました。バス代行になっているのです。掲示してあるインフォーメーションを見るとチェコ語で詳細は理解できませんでしたが、2025年8月から2025年12月まで工事のため、バス代行と書いてあるようです。うーん、一か月遅かったかと一気にモチベーションが下がりました。とりあえずバスに乗ってベヒニェへ行ってみました。途中、線路には工事用の車両が乗っかっています。もしかしたら、1500vから3000vへの昇圧があるのでしょうか。詳細はやはり判りません。結局、ベヒニェにも撮りたかった機関車はいませんでした。
気を取り直してターボルの街を散策することにします。街では、ほとんどアジア系の人を見かけません。この街は、フス戦争で急進派の拠点となったことで有名です。街の中心ジシカ広場には変容教会がありました。変容教会と言えば、有名な「キリストの変容」です。この教会は、「キリストの変容」を記念して建立されたものなのです。「キリストの変容」の舞台はイスラエルのタボル山です。なるほど、ゆえにこの街はターボルと名付けられたのかなと勝手に想像しました。
-
ターボル